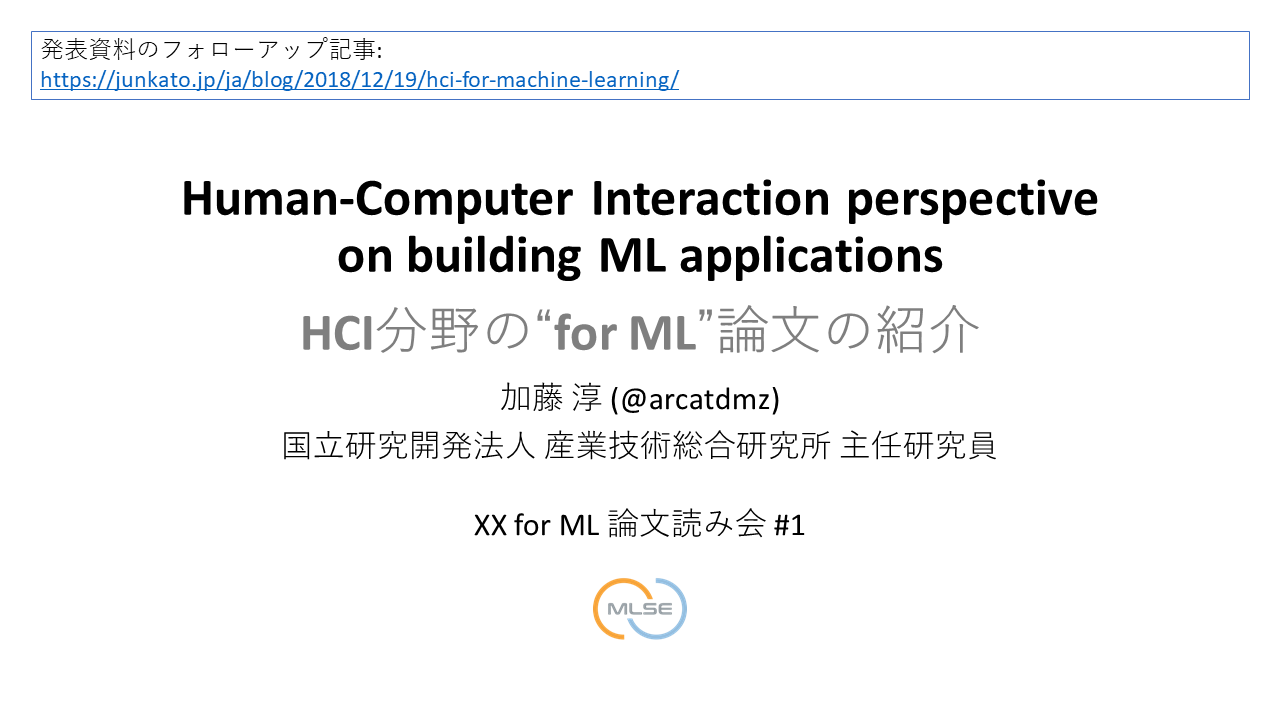GUI と HCI の理論研究(フランス在外研究に至った経緯)
GUI(グラフィカルユーザインタフェース)には、まだまだ研究の余地があり、個別のインタラクション設計でなくその背後にある理論の研究はとくに発展の余地が大きいのではないでしょうか。HCIの強みは工学的に構成したインタラクティブシステムという人工物をバウンダリオブジェクトととして議論を展開できるところにあり、その観点では、未来のシステム設計だけでなく、現存する、あるいは過去のシステムやツールを対象とした研究アプローチが今後さらに重要になると考えています。
 トップ
トップ