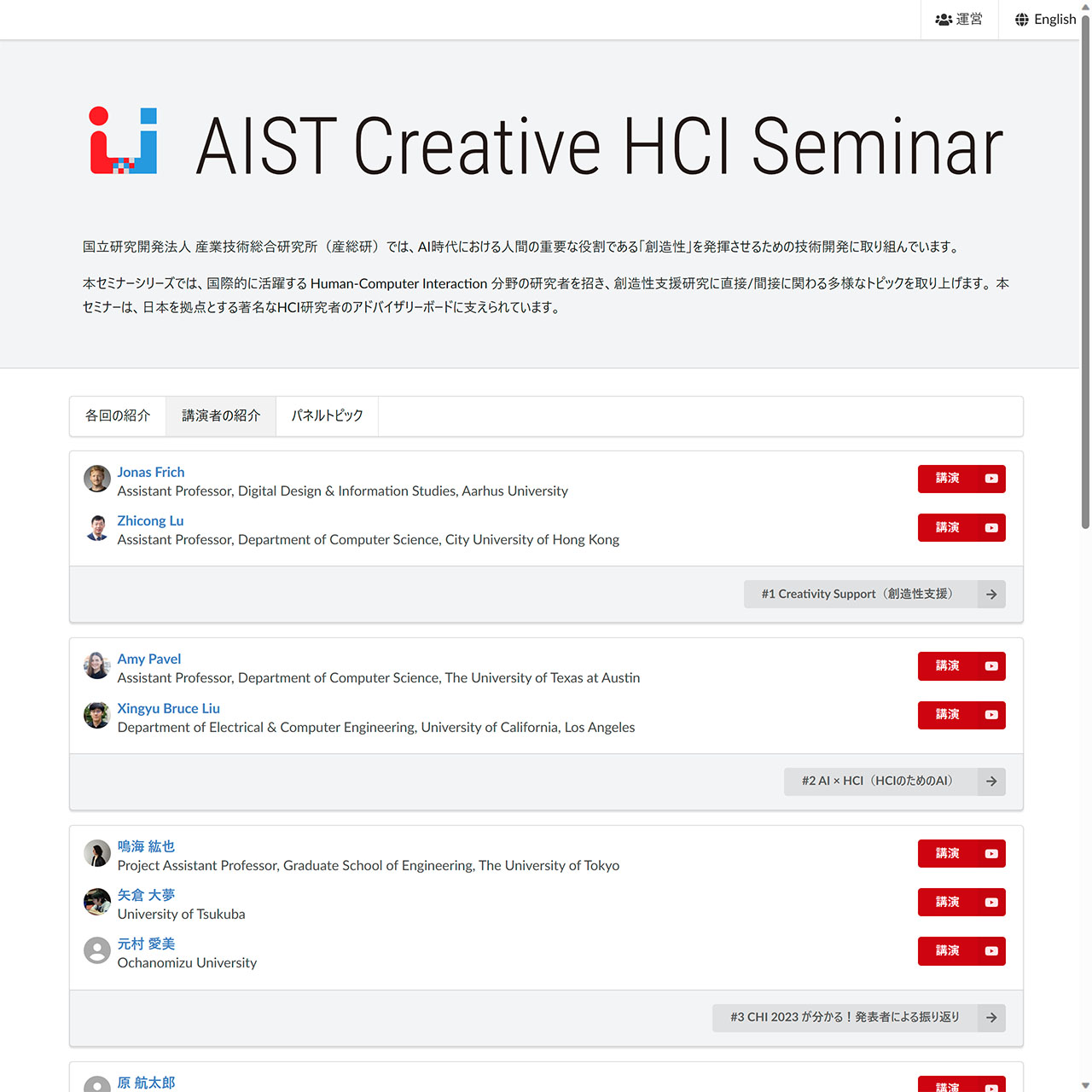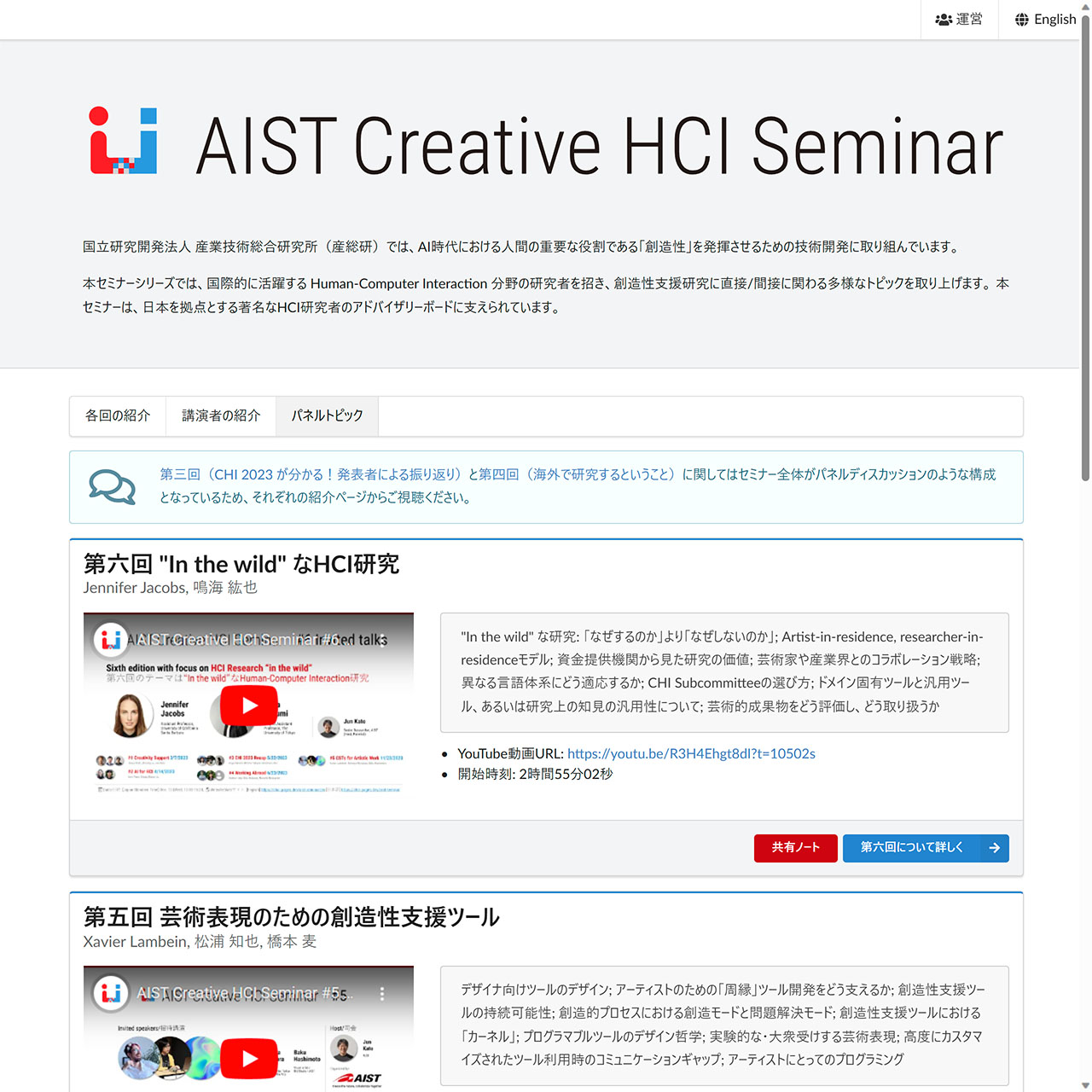HCI research in the wild, why not?
気付けば大晦日元旦になってしまいました。 Human-Computer Interaction (HCI) Advent Calendar 2023 最終日に公開するつもりだった記事ですが、体調を崩して、はからずもゆっくり過ごす年末年始でした。みなさんもどうか体調に気をつけて、よい一年をお過ごしください。
この Advent Calendar は毎年いろいろな話題が出るので、一読者としても楽しみにしています。2023 年分は自分が最後なので、主に国際連携・メタ研究の観点でやったこと三つを振り返りながら、後だしじゃんけん的に、いくつかの記事を読みながら考えたことを書いてみます。やったことの振り返りは、昔は定期的にブログ記事にしていたのですが、今見返したら5 年前にやって以来、諦めていたことが分かりました。
CHI 2023: Special Interest Group on Creativity and Cultures in Computing
4 月はドイツ・ハンブルク開催の CHI 2023 で研究会合(Special Interest Group; SIG)を開催しました。2022 年の Advent Calendarのタイトル「コンピュータありきの創造性と文化について」がそのまま SIG のタイトルになっています。
もともと 2022 年 6 月にオーフス大学を訪ね、創造性支援に関して重要な文献を多数発表している若手研究者 Jonas Frich と議論したことがきっかけで会合提案したのが通ったもので、一年越しの開催と考えるとそこそこの準備期間がありそうですが、実態としては、まさに前の Advent Calendar を書いたタイミングが会合提案の〆切(December 15, 2022 AoE)で、数週間の駆け込みで座組みを確定しつつ提案を書ききりました。その後、私が最初に声をかけた Jonas と Zhicong を日本に招いて作戦会議をしたのが 2023 年 3 月(第一回 AIST Creative HCI Seminarのタイミング)、あとは 4 月中旬に CHI の Web サイトが更新されるタイミングと同時にイベントの公式 Web ページを立ち上げ(当時の Git コミット)、共同提案者のリーチできるコミュニティで参加を募って、盛会を祈りました。

ふたを開けてみれば、用意してもらった部屋が満席で、多少立ち見も出ていたようです。また、テーマ面では、2022 年の記事や学生向け雑誌 ACM XRDS (Crossroads)向けの寄稿で言及してきた私見が、時流と、コミュニティレベルでの関心とうまくマッチした結果だと思っています。私個人として関心を持ち続けてきた環境や文化と創造性の関わりが、AI 技術の興隆で、より多くの人々の興味の対象になってきたのです。
HCI の 3 つの波と道具、システム、環境
Advent Calendar 22 日目の記事で中川さんが HCI の「3 つの波」について紹介していて(私の記事への言及もありがとうございます!)それに続く 4 つ目の波として AI ありきの「比較的受動的な」「意識低い系」インタラクションに言及されているのはとても興味深いです。パラメタ空間の探索可能性を向上して自由度を上げることがインタラクション設計の唯一解ではありません。クリエイティブ系職種の創造的プロセスにおいてすら、最終成果に貢献しないけれど、当人のモチベーション維持のためだけに必要不可欠な戦略があったりするわけで [Nicholas et al., C&C '22]、この脆弱で愛すべき存在とコンピュータがどう共存すべきかという問いには、シンプルに前向きな課題解決型の研究だけで答えることは不可能です。
話は変わりますが、日本の情報処理学会には、もともとヒューマンインタフェース研究会という研究会があったそうです。これが 2007 年にヒューマンコンピュータインタラクション研究会へ改称されるタイミングで、おそらくできたての産業技術総合研究所 臨海副都心センターで記念回が開催され、これに併せて主査の中小路先生(現 Japan SIGCHI Chapter Chair)が「インタフェースからインタラクションへ」という文章を残されています。ここでは新名称について
人間が居て、技術が存在して、その間のインタフェースを考えるのみではなく、人間と技術との相互作用としての系そのものを研究の対象とするコミュニティの現状を、より適切に表現する名称
と書かれています。(3 章も興味深いので、ぜひ読んでみてください。)
私が研究の場に足を踏み入れたのが五十嵐 ERATO が始まった 2008 年なので、「インタラクション」研究会へのシフトが完了した直後ですね。当初はユーザインタフェースあるいは単一の道具の発明で課題解決するタイプの研究をしていました。 ただ、想定されるワークフローを支援するため複数のユーザインタフェースを備えたプログラミング環境の研究をして以来、徐々に、複数の道具や、人までも含めた「環境」の中に置かれた人 [Kato and Shimakage, 2020] という絵を描くようになりました。人の能動性に応えるだけでなく、人を楽しませ、人を触発し、人と人の共創を促す環境について考えてきました。情報技術が人々の生活を覆うようになった今 [Andreessen, 2011]、HCI 研究はどういう環境を作るべきか?を提案していく必要があると思っています。特定のツールやユーザインタフェースに関する研究であれば、それがどういう環境を構成する部品となるか?という問いになると思います。
ここまでの道具、系(システム)、環境へのフォーカスは、大まかに HCI の「3 つの波」とマッピングでき、非常に単純化して見れば、研究対象が徐々に拡大しています。すべての環境は文化の影響下にあり、文化もまたそこにいる人々によって長期的に形作られていくということに着目すれば、次のステップは文化差を考慮に入れたインタラクション設計、あるいは文化を形成するインタラクション設計という見方もできそうです。この話題にはまたあとで戻ってきます。
LIVE 2023: The Ninth Workshop on Live Programming
10 月はポルトガル・カシュカイシュ開催の SPLASH 2023 で Live Programming に関する唯一の国際ワークショップ LIVE 2023 を開催しました。
SPLASH はプログラミング言語(PL)系の会議なので、どこが HCI なんだと思われるかもしれませんが、まず SPLASH の最後の 2 字は Software for Humanity の略ですし、LIVE の説明には "Whereas PL research traditionally focuses on programs, LIVE focuses more on the activity of programming."(古典的 PL 研究はプログラムを重点的に扱うが、LIVE はプログラミングという行為に、より重きを置く)とあり、実際 SPLASH における技術系 HCI 論文の多くがこのワークショップに集まるようになっています。
私はこのワークショップの Steering Committee の一人で、前年に続いて共同委員長を務めています。LIVE 2023 の共同委員長は Ink & Switch という独立系ラボをリードしている Peter van Hardenberg にお願いしました。じつは Peter は前年の LIVE 2022 招待講演にお呼びしており、そのうえ LIVE 2023 の共同委員長の依頼を請けてくれているので感謝してもしきれません。ただ、それだけ彼(と彼のラボ)の興味が LIVE とオーバーラップしているわけで、おそらく来年 LIVE 2024 の共同委員長も引き続き務めてくれるのではないかと思っています。

ワークショップは非常に盛会で、毎回参加している人からも最高の回だったと言ってもらえて、大変報われる思いでした。LLM、ドキュメント指向プログラミング(Jupyterみたいなもの)、インタラクティブなデバッグ手法、ゲームづくりや音楽制作など創作のためのプログラミングなど、幅広いテーマで魅力的な講演が集結したことが大きかったと思います。 LIVE 2023 は、いわゆるアカデミアにふだん縁がない人にも積極的に門戸を開くワークショップにしたいと考えていました。そこで、運営サイドとしてとくに気をつけたことは、主に以下の三点に集約されます。
- 査読を担当してくれるプログラム委員の選定に非常に気を配ること
- 投稿してくれそうな有望な人には個別に声をかけること
- 当日のシミュレーションをしながらセッション編成を入念に行うこと
まず一点目は、私が個人的に力を入れた点です。トップ国際会議では予稿集に採録される論文本文が、会議の重要な成果物となりますが、LIVE に関しては、ワークショップの場が最大の価値であると考えており、一般的な論文だけでなくデモ動画だけの投稿も受け付けています。それでも学術会議の一イベントであることから、研究上の文脈を踏まえた内容に軌道修正が必要となることもあります。このバランス感を実現する唯一のチャンスが査読プロセスであり、分野の知見を持っていることだけでなく、建設的で情報量の多い査読を書いてくれている人たちにプログラム委員をお願いすることができたことは、間違いなくプログラムのクオリティによい影響を与えたと思っています。こうした委員職が初めての人たちがいましたので、声をかける最初のタイミングから査読プロセスの全体像を示すなど、委員の方々とのコミュニケーションにも気を使いました。
二点目は、Peter に大いに頼ったところです。私は前年までの LIVE の参加者や投稿者のことはそれなりに知っていましたが、どうしてもアカデミックな文脈、それも HCI 関係の人たちに偏りがちです。 Peter は開発者向けの会議にも多く顔を出しており、面白いシステムを研究開発している人たちをよく知っていました。 LIVE 2023 はスケジュールの都合上、招待講演を誰かに依頼することをやめたのですが、その過程で Peter が挙げてくれた候補は非常に勉強になりました。
さて、学術会議において、ワークショップという形式が本当に「ワークショップ」だったことはどれくらいあるでしょうか?自分の経験では、プレゼンテーションと質疑応答が続いて、聴衆が受動的な立場に終始することが大方です。三点目に関して、私の発案で LIVE 2022 から、全参加者の自己紹介タイムを入れていたのですが、 LIVE 2023 はさらに、セッションの括りを入念に検討し、質疑応答部分をパネルセッションのようにできないかなど、Peter と私とで事前にいろいろ議論しました。ちなみに、参加者が少人数の場合は Writer's Workshop という形式が、私が知るもののなかでいちばん「ワークショップ」的ですが、LIVE はもっと参加人数が多いので、そこまで形式に手を加えることはしませんでした。



LIVE が盛会に終わってから、別日に、 Ink & Switch がスポンサーとなって Unconference が開催されました。これは通常の会議(conference)と異なり、セッションテーマをその場で決めるインフォーマルな議論の場です。私は一参加者として楽しませていただいたのですが、これも、ワークショップを補完するイベントとして、非常に有効だったと思います。とくに、刺激的な講演をたくさん聴いたあとの感想戦としての役割と、講演者と聴衆の立場を超えた交流の機会としての役割があったように感じました。個人的にも、「LIVE の共同委員長をやっていること以外、何も知らなかったから、話が聞けてよかった」というふうに何度か言ってもらえて大変よかったです。運営サイドの人のことって意外と見えないものですよね。
日本の HCI 世界の HCI
Advent Calendar 初日の荒川さんのWISS 参加記では、WISS(あるいは日本の HCI) の研究の多くが個々人のモチベーションからボトムアップ的に出てきており、よいことだけれども、それを HCI の国際的研究パラダイムに接続できていない課題があるのではないかという主旨の指摘をしています。私はこの指摘について基本的には同じ意見で、主に二つの感想を持っています。
第一に、日本の HCI では、新規性の有無以外に、研究の意義について議論する機会(あるいは、自分がやっている研究がなぜ「面白く」「重要なのか」きちんと言語化する機会)があまり多くないように感じます。 WISS の昼のセッション+ナイトセッションという構成は、上記の LIVE のワークショップ+アンカンファレンスとまったく同じで、荒川さんが触発されているように、おそらく稀有な機会になっています。ただ、LIVE で出会った研究者は普段からこうした議論を行っている形跡がありました。アンカンファレンス開始時点でトピック提案者が全参加者相手にそのトピックについてピッチするのですが、一朝一夕で考えられたものとは思えない問題意識が次々出てきて、それ自体が非常に面白かったのです。
私としては、そういう場をもっと作ることがプロ研究者の役割の一つと思って、さまざまなイベントを運営し、多くの方々を巻き込んできたわけで、同様の取り組みはもっと広がるといいなと思っています。Advent Calendar 12 日目の元村さんは後述のセミナー運営協力で海外から招聘した研究者と交流する機会を作り、博士進学も決められたそうで、こうした例は企画者冥利に尽きます。仮に学生向けにアドバイスするならば、個々の研究テーマを超えた議論をプロ研究者に吹っかけるというのは、いいスターティングポイントではないでしょうか。ポイントは、自分に対する研究指導の一環としてアドバイスを求めるのではなく、インタビュアーのように聞く側に回ることです。私自身、幸運にも 2023 年何回か学生にチャレンジされる機会があり、とても楽しかったです。ちなみに、多くの学生にとって、これを真正面から問われる側になる最初の機会が博士論文ですね。シニアの胸を借りておくのは、その準備運動としても悪くないでしょう。
第二に、国際的研究パラダイムとは何なのか、という問題があります。荒川さんの記事でも参照されているとおり、CHI は一枚岩のコミュニティでなく、多様な研究が同居しています。グランドチャレンジがないことが長年の課題と見る向きもあるくらい、学際的で、流動的で、さまざまな波が存在していることが分野の特徴の一つとも言えるかもしれません。そのうえで、メタ研究的な議論は英語で行われてきており、英語圏の研究コミュニティは常に下駄をはいた状態で国際学会と共に成長してきています。とくに名門の HCI コースは、博士課程学生・ポスドクの就活シーズンとか、学会にかこつけてとか、何もしなくとも定期的に国際的に名の知れた若手研究者が訪問して講演していきますから、パラダイムを形成する現場を目撃できていることになります。
もう少しいえば、コンピュータは人工物、論文も人工物ですから、研究パラダイムも広い意味で人工物であり、学会における人間関係、例えば「権威」から無縁ではありません。CHI のことをトップ国際会議と呼ぶようになって久しいと思いますが、そもそも「トップ」とは何なのでしょうか。私は感覚的に、こうした会議に論文を通せる人たちとそうでない人たちの間には、論文執筆、改訂にかける労力(あるいは認識)について越えられない溝があると思っていますが、「トップ」としての立場は、そうした即自的性質とは別に、特定の文化資本・社会資本を持つ人々の間で「作られてきた」側面があると思っています。
トップ国際会議に論文を通すことを一種のゲームだと捉える向きもありますが、私はそれ自体がむなしい行為だとは思いません。制度化された学問はすべてゲームと見なすことができ、現代社会においてそうした制度化はある程度、受忍するしかありません。それがむなしい行為になるのは、多数の研究者が、価値判断の指標を無批判に外部化してしまった瞬間です。ですから、話が最初に戻りますが、研究がなぜ「面白く」「重要なのか」きちんと言語化し続けることは重要なのです。(偉そうに書いてますが、自分がちゃんとできているとは思っていません。。何だかんだいって the 日本の HCI 研究者なので、少しずつ勉強しているつもりです。)
こうした話が通じる仲間と共に、コミュニティとして学問を問い直し続けることが、健全な HCI の未来に不可欠なのだろうと思います。例えば、 CHI 2023 でアフリカのアントレプレナーが招待講演者だったのは、欧米中心であった WEIRD な HCI コミュニティによる自己批判的な側面が大きいと思いますが、これが欧米にとって都合のいい「多様性」のサンプルとして消費されて終わりにならないよう、歩みを進めていく必要があるでしょう。
AIST Creative HCI Seminar
12 月 13 日(水) 第六回 AIST Creative HCI Seminar を開催しました。これは 3 月に始めた一連のセミナーシリーズの暫定的な最終回で、 University of California Santa Barbara の Jennifer Jacobs 氏を東京大学 目白台インターナショナル・ビレッジに物理的に招聘して、東京大学の鳴海 紘也氏とともに講演・パネルディスカッションに参加いただきました。現地の模様は Zoom Webinar でも配信しており、アーカイブを YouTube でご覧いただけます。
セミナーシリーズは CHI 〆切の前後(+ 加藤の夏イベント関連の繁忙期)を除く 3, 4, 5, 6, 11, 12 月に計 6 回開催しました。Web サイトを見ていただくと分かるのですが、国内イベントではあるものの、一貫して英語で講演いただき、パネルディスカッションなどもすべて基本的に英語で運営してきました。Web サイトも日英両方用意しており、物理開催の初回と第六回だけでなく、他の回もオンラインでの英語圏からの参加者が一定数いたことを確認しています。海外研究者の招聘費用など諸々は産業技術総合研究所持ちであり、その手厚いサポートがなければ実現できなかったシリーズなので、所属の(そして日本 HCI の)英語圏での宣伝になっていればと願う次第です。

このシリーズは HCI 分野を概観するという野望のもと始めたのですが、実際には扱えていないテーマがたくさんあります。例えば UbiComp, Computational Interaction, Crowdsourcing, XR, Education, Entertainment, Usable Privacy, Visualization など、枚挙にいとまがありません。どなたかに引き継いでもらえると嬉しい気持ちもあります。
ただ、結果的に私の趣味性というか、問題意識がかなり反映されたテーマ編成になっていて、それはそれで意義があったように思います。例えば、初回と最終回の海外からの招待講演者は全員 CHI 2023 での研究会合 SIGCCC の共同提案者です。私としては、各回のパネルディスカッションを通して「コンピュータありきの創造性と文化について」考えを深めることができました。
10 年後も有効であろう研究上の論点がいろいろ出てきたと思うので、ぜひお正月に講演とパネルディスカッションを見ていただけると嬉しいです。
Generalizability の幻想
Advent Calendar 8 日目の栗林さんの CHI 2023 論文裏話は、研究テーマこそまったく違うものの、非常に首肯するところの多い記事でした。また、セミナー最終回のパネルディスカッションで触れた内容との重複も大きいと思います。
まず共著者に全盲の研究者がいたのに参加型デザインプロセスと認められていない点、記事の上では涼しい顔でスルーされたように書かれていますが、CHI のコミュニティノルムの限界を示しているようにも感じました。査読者に好意的に解釈するならば、件の研究者は情報技術に精通しすぎているから、当事者の例としては適さない、ということでしょうか。本当に?
私も以前、論文投稿でドメインがかなり絞られる制作ツールの論文を投稿して共著に当事者二名を入れたところ、当事者の経験に基づくデザイン指針はサンプルサイズが小さすぎてどの程度そのコミュニティを代表しているか分からないし、真実性を検証できないため問題であると指摘され、かなり絶望的な気分になったことがあります。では、どうしたらよかったのでしょう。二人を共著者から除いて、外部の実験協力者として扱えばバイアスが除かれるんでしょうか?それとも、信頼関係を築いてきたプロ相手に話を聞くのを諦め、より幅広にリーチして、表層的なコメントしかしないリスクを許容するべきでしょうか。ユーザビリティ評価で 5 人にインタビューしたら論点がサチることが知られているのに?
あと、私の研究でよくある批判が、応用領域がニッチである、というものです。例えば CHI 2023 で発表したリリックアプリに関しても、そうした批判がありました。「歌詞が魅力的にアニメーションするインタラクティブなビジュアルアート」という新たなメディア様式を提案しているのだから、ニッチで当たり前じゃないですか。世の中にまだないから、初音ミク「マジカルミライ」のプログラミング・コンテストを通してその可能性を検証しているわけです。毎年素晴らしいリリックアプリの作品が出続けています。これ以上何を求めているんでしょうか。こうした査読をもらうと、まず査読者への怒りが湧き、コミュニティへの失望と悲しみに変わります。数日寝かせた後、コンテストの模様などを思い浮かべながら、地道に反駁していく勇気をもらうのです。リリックアプリの場合にどういった反論をしたかについては、ほぼ論文内部に記録されている(7 章)ので、ぜひ参考にしてみてください。
私はこれらの問題をまとめて「Generalizability(一般化可能性)の幻想」とか呪縛というふうに呼んでいます。 Jennifer は「ニッチ(niche)とドメイン固有(domain-specific)は違う」と表現していたと思います。 セミナー初回で講演してくれた Jonas の論文では、ラボスタディで終始するタイプの創造性支援研究の限界が指摘されています。ツール設計者も実験協力者も WEIRD な文脈に置かれた大学院生である場合に、それが極めて「ニッチ」なコンテキストであるという限界がまったく意識されていない、という問題があるのです。 つまり、研究上の知見においてはその generalizability が重要だという批判は、もし上記のようなケースに向けるのであれば、同様に多数の典型的な HCI 研究に対しても向けられなければならないでしょう。
実際には、研究上の知見が generalizable であるかどうかという問いにはあまり意味はないと、私は考えています。 本質的に重要なのは、その研究がどういった文脈の上に置かれ、どういったドメインを扱っているかについて常に自覚的であることです。常に limitation を明示すること、という言い方もあるかと思いますが、私はもう少し建設的でオープンな表現として「自覚的であること」のほうを好みます。むしろ文脈・ドメインが extreme であるほど技術の限界を押し広げる厳しい要求があり、より豊かな知見を得ることができる、という考え方もあり、私はこちらに与します。
おわりに: "In the wild" な HCI 研究
2023 年は、自身の主著論文発表 [Kato and Goto, CHI '23] や人文系学会での登壇発表 [Kato, SAS 34]、学生向け学会誌への寄稿 [Kato, XRDS 29(4)]、マジカルミライでのイベント登壇、菅野さん落合さんとの鼎談など、私個人のクレジットが入るタイプの活動もいろいろやりました。ただ、これらは 5 年前の振り返りと比べてみてもこれまでの活動の延長に近いものと言えます。やはり、三つのイベント運営において国際的な場づくりを意識したことが新機軸であり印象に残った一年となりました。
すべてのイベントに共通するのが「現場(in the wild)」意識でした。
- LIVE は単なる研究者集会を超え、ふだんであれば開発者イベントにしか顔を出さないような人々も集まることで、興味深い事例が集まり、活発な議論が起こっていました
- SIGCCC・セミナー初回では Zhicong Lu が VTuber や中国辺縁部でのライブ配信など、現実世界とは異なるバーチャルなコミュニケーションについて、参与観察を通して迫った研究を紹介してくれました
- SIGCCC・セミナー最終回では Jennifer Jacobs が陶芸家のアーティスト・イン・レジデンスを運営した事例などを紹介し、デジタル技術と芸術家のアナログな手技の見事な融合を果たした研究を紹介してくれました
- セミナー第五回では研究者兼実践家の松浦さん、ビジュアルアーティストだが明らかに研究要素を含む実践を進めている麦さん、LIVE でも講演してくれた Xavier Lambein が魅力的な研究を紹介してくれました
- 各イベントで折に触れて紹介した私の研究は、長期にわたりコミュニティで築かれた信頼関係の上で、現場の協力があってはじめて可能になったものです
いずれも、何らかの文化に根差して研究を推し進めてきた事例と言えます。そして興味深いことに、そのアプローチは非常に多彩です。当事者の言語コードを査読を通して研究側に寄せたり、文化人類学的な手法を用いたり、アーティスト・イン・レジデンスを活用したり、当事者研究をしたり。おそらくまだ見ぬアプローチもあることでしょう。SIGCCC の共同提案者である中小路先生は哲学に興味があると仰っていました。私はメディア論やメディア考古学から学べることは多いのではないかと考えています。
多様性を認め合う情報化社会になって明らかになってきたのは、社会に質的な中心などなく、あらゆる場所が辺縁であり、土着の文化の影響を免れないということ、そして、情報技術は従来のメディア技術とまったく同様に、メディア固有の文化形成過程を実現するということではないでしょうか。しかし従来と異なり技術そのものが変幻自在かつ偏在しており、技術者が社会に大きな影響を及ぼせることから、より一層の注意を払いながら研究開発を進めていかなければ、危うい結末が待っています。 HCI 研究は、例外なく何らかの文化的文脈に置かれ、特定のドメインを扱っていますが、そうした当事者性に無自覚なままではいられなくなってきているように思います。
セミナー最終回のパネルでは、「どういうタイプの HCI 研究が、 "In the wild" な研究の恩恵に与かれるんでしょう、なぜ "In the wild" でやるべきなんでしょうか。」という主旨の質問がありました。もちろん、大多数の研究者は、私がやったように Web サービスを運営しながら 8 年越しで新しい研究論文を出すほどのんびりとはしていられないでしょう。Jennifer がやったように好待遇でアーティスト・イン・レジデンスを運営することも、日本の公的研究費のシステムでは難しいかもしれません。
Jennifer の回答は「それは Why ではなく Why not の問いだと思う」というものでした。つまり、なぜ "in the wild" でやるのかでなく、なぜできないのかのほうを問うべきなのです。既存事例とまったく同じことをする必要はないし、すべきではありません。しかし私は、その本質をうまく言語化し、社会文化的背景を考慮に入れることを研究コミュニティとしてある程度コード化できれば、HCI は、人類にとってもっと重要な役割を果たせると思っています。(直前に Advent Calendar 24 日目、矢倉さんの 「HCI」と「おもちゃ」と「学術領域」 の記事が出ていたので、併せてどうぞ。)
今年も HCI 研究、やっていきましょう!
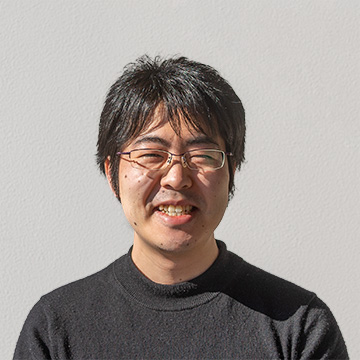 トップ
トップ