コンヴィヴィアリティ・創造・研究(“現実”の自給自足展に寄せて)
2 月 16 日(水)、中目黒の N&A Art SITE で開催された島影さんによる「“現実”の自給自足展」に、菅野さんとお呼ばれしました。「情報工学“研究”の民主化」という演目に出ました。この美術展での研究の美学についての対話をきっかけに、イヴァンイリイチの「コンヴィヴィアリティのための道具」とこれまでの取り組みの関係、創造性について最近読んだ本で面白かった内容、研究者としての心構えについてまとめて書きました。
美術展で研究という創造を論じる
メンバーと演目だけ聞くと研究会のパネルセッションか何かか?と思われそうですが、この公開インタビュー(展示)を現代アートの文脈で敢行したのが島影さんのすごいところですね。実際、いったい何の話をするのかそのときになるまで分からなかったのですが、振り返ってみればこのメンバーと場所ならではの対話になっていたと思います。
当日の模様は Podcast 形式ですでに公開されています。
私も菅野さんも、論文を書くというアウトプット以上のことを研究に求めてきました。具体的には、二人とも、研究の受益者(当事者)を巻き込んだ研究プロセスを大事にしている点、研究コミュニティ内の文化に縛られず他分野や社会との接続を意識している点などが共通しています。
この美術展での対話は、こうした創造的研究姿勢を美学(aesthetics)として捉え、アートの文脈でクリティカルに語るという取り組みだったと理解しています。私の研究活動のなかに美を見出してくれた島影さんに感謝しています。
コンヴィヴィアリティのための道具
私と島影さんはCHI 2015 でのワークショップ以来のお付き合いで、お互いコンピュータというプログラマブルな「道具」による創造的活動に興味を持って活動してきたところが共通しています。たとえば、目が見えづらい人が島影さんたちのオトングラスというツールキットを使って自分なりのスマートグラスを設計することや、TextAliveを使ってリリックビデオを作ることです。
どちらも、人々が広義のプログラミングによって自身の創造性を発揮できるようにする技術的な取り組みであり、2020 年には、そのことについてConvivial Computing Salonという国際ワークショップで共著の発表を行いました。このワークショップは Ivan Illich による "Tools for Conviviality" (コンヴィヴィアリティのための道具, 1973)という書籍で提唱されている「コンヴィヴィアル」なコンピューティングの実現に向けた取り組みを募集したものです。
Illich は、1960 年代以降の技術革新と資本主義経済の発展に伴い、産業主義的な考え方が各所に根付いていったことを批判しました。具体的には、教育や医療が標準化され、科学技術が高度化して機械が発展、普及するなかで、社会の校舎化、病棟化、獄舎化が進み、人々が自ら学び、健康を管理し、自身の技術を身につける機会が棄損されていると指摘しています。
Illich はこうした学校の制度や病院の仕組み、機械が導入された商品の生産施設まで含めて「合理的に考案された工夫すべて(文庫版訳書 p.58)」を広義の「道具」として扱っており、産業主義的に行き過ぎた道具の用い方を改めるべきだとしています。そのために、「それを用いる各人に、己の想像力の結果として環境をゆたかなものにする最大の機会を与える(文庫版訳書 p.59)」コンヴィヴィアリティのための道具(自立共生的道具)こそが肝要であると述べています。
つくることで祝祭に参加する
私たちは、まさにコンヴィヴィアリティのための道具を研究開発してきたのだと思います。ただ、 Illich のいうコンヴィヴィアルな社会像が個々人の自立を大前提にしており、個人主義的な価値観が重視されているように見える(それゆえに自立共生的と訳されているのだと思います)のに対し、私たちは人々の協働関係に注目してきました。
私たちの取り組みは複数名の協働する環境づくりですから、いわゆる Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) 的な文脈でも解釈可能です。ただ、多くの CSCW 研究が同じ役割を持つ複数名による協働を対象としているのに対し、私たちは多様な技術的文化的背景を持った人々の協働を支援しています。 これは、 Illich の用法よりも一般的な意味(宴会とか祝祭の愉しみを与えてくれる)に近いコンヴィヴィアルな環境づくりの取り組みといえるかもしれません。そうした創造的な環境を、島影さんは Personal Fabrication によって成立するビオトープ、「ファブビオトープ」と呼んでいます。
私はコンピュータ科学のバックグラウンドからきているので、まず CSCW に目がいってしまうのですが、最近では、むしろ文化人類学とかメディアスタディーズの文献にあたったほうがよいのではないかと思うようになってきました。 例えばアーチ海外展開顧問で文化人類学者の三原さんから教えてもらった "The Soul of Anime -- Collaborative Creativity and Japan's Media Success Story" (アニメの魂 ── 協働する創造の現場, 2013)という書籍があります。これはアニメづくりの現場にいる多職種のクリエイタから作品を享受するファンまでが織りなす協働的ネットワークを、緻密なフィールドワークから明らかにしていくというものです。
また、本書でも参照されている Henry Jenkins による "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide" (コンヴァージェンス・カルチャー ── ファンとメディアがつくる参加型文化, 2006)は原著こそ 2006 年刊ですが、昨年訳書が出たもので、国内でにわかに注目を集めているようです。 1. テクノロジーに対する広範なアクセス、2. テクノロジーによって実現する新しい種類の社会的交流への馴れ、3. メディア・コンヴァージェンスに応えて消費者が発達させたコンピュータ・スキルの完全な熟達(訳書 p.57)という三点セットによって消費者(ファン)が創作文化を不可逆に変容させたことを、自らをファンと自認する著者(academic fan; aka-fan)が多様な事例とともに説明しています。
さらに、越境する認知科学シリーズ最新刊の「ファンカルチャーのデザイン ── 彼女らはいかに学び、創り、『推す』のか」(2021)は、フィールドワークでの実体験をもとにした軽妙な語り口で、ファンカルチャーに生きる人たちに見られる非産業主義的な学習過程について豊富な参考文献とともに紹介しています。 Illich の "Tools for Conviviality" や "Deschooling Society" (脱学校の社会, 1971)、 Jenkins の "Textual Poachers" (二次創作を志向してテクストを読むファンたちのこと, 訳書未出版, 1992)を踏まえた議論が展開されており、ここまでに挙げた書籍での議論をファンカルチャーというトピックで串刺しにする一冊でした。サブタイトルでは「学び、創り、『推す』」と 3 つの活動が並記されているように読めますが、中身を読むとこれらすべてが創造的行為だと分かります。
産業主義的価値観では創造と見なされないことでも、個人にとって意味のある創造(little-c)はたくさんあり、そうした創造が自立共生的に交歓されることによって、より大きな協働的ネットワーク ── 祝祭的な文化活動が駆動されているのだと思います。
非参加のアイデンティティ
翻って私自身の研究者としての活動について考えてみると、これは美術展での対話の中でも繰り返し話題に上がったことですが、論文発表のインパクト最大化よりも大切にしてきたことがあるように思います。
自分としては論文発表も大切だと思っているのですが、Web サービスや API の一般公開、実証実験を通した成果の社会展開(TextAlive 関連は「研究開発の自由度と互換性の両立」にまとめました)、アーチでの兼業(Arch ResearchのPIとして冊子「アニメ技術」の刊行やツール開発などを主導)など、論文にならないことを進んでやっています。
ところで、先に挙げた「ファンカルチャーのデザイン」で、学習は共同体への参加過程であり、学習時の社会的状況と切り離して考えることはできないという「状況的学習論」について知りました。 Étienne Wenger 氏は UC Irvine の情報・コンピュータ科学専攻に提出した博士論文 "Toward a theory of cultural transparency : elements of a social discourse of the visible and the invisible" (1990)で、保険会社におけるフィールドワークをもとにこの理論を提唱しています。
この保険会社では、請求処理係が、計算式の記されたCOBシートという道具を使って保険請求を処理するのですが、このシートは計算式の意義を理解せずとも使えてしまうもの(Illich の批判するところの操作的な道具)になっていたそうです。また、請求処理係が保険契約者と対話する際、親身になると大きな精神的負荷がかかってしまい、業務効率が落ちてしまいます。 そこで、請求処理係の中には、あえて請求処理の仕事との距離を維持すること、自分を高めず、請求処理係にならないことを重要視する人たちがいました。(状況的学習論の両義性および動的特質 ── ウェンガーの学位論文の検討を通じて, p.4)このように、あえて規範構造からの距離をとる、非参加という参加形態がもたらすアイデンティティを「非参加のアイデンティティ」と呼びます。
学会というコミュニティの中で評価されるためには、論文発表が最も効率的です。ただし、論文のための研究とは研究の産業主義化であり、コミュニティ全体で見ればゆるやかな自死に加担することに他ならないと思います。論文の集積はコミュニティの重要な側面ですが、同時に、一側面に過ぎません。
学会の規範構造から外れたところにもアイデンティティを持つことは、私にとって、コミュニティへ中長期的に貢献し、自身も楽しく生きるための、一種の方法論なのです。
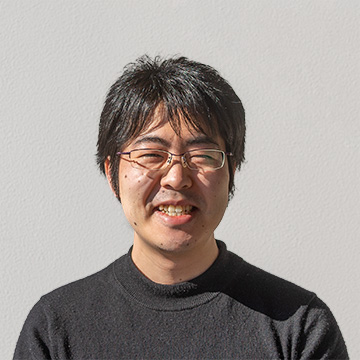 トップ
トップ