研究の知と論文
兼業先のアーチでは 2018 年から絵コンテ制作支援の研究開発を行ってきました。その成果の一環で、国際アニメーション学会(Society for Animation Studies; SAS)で絵コンテの歴史と現状、課題についてまとめて講演する機会を得ました。おかげさまで、関係各所から興味を持って見ていただいているようで、ありがたい限りです。
ところで、じつはこの研究、同じトピックで Human-Computer Interaction 系の国際会議に論文投稿して不採録になった過去があります。初めからうまくいっているわけではないのです。この経験から、研究によって生まれる知と、それを報告するための論文というフォーマットについて考えたことを書き留めておこうと思います。
今回の発表内容自体は下記ツイートや Facebook の投稿、発表スライドをご覧ください。
二度の不採録
今回の講演は絵コンテの過去、現在、未来を順に紹介するものになっています。未来はおまけです。ところが、研究開発を始めた当初は、このバランスが逆でした。
最初に投稿して不採録になった論文は、きわめて未来志向でした。絵コンテが果たすべき役割や、制作支援ツールが満たすべき要件について監督やプロデューサーと議論した内容をまとめ、デザイン指針として報告する内容でした。不採録の理由は、この研究プロセスが正当な科学的アプローチに見えないというものでした。読者としては、身内とちょっと喋った内容をつまみ食いして報告しているだけなのではないか?という疑念を払いきれなかったということですね。
そこで論文を改訂し、絵コンテの現状についてのより詳細な説明と分析を加えたのですが、こちらも不採録でした。論旨は初稿のときよりも複雑になっていました。絵コンテがアニメ制作プロセスにおいて果たす役割を、プリプロダクション(絵コンテが監督によって作られる過程)とプロダクション(絵コンテがアニメーターなどによって利用される過程)に分けて考え、役割のプロセス中での変化を考慮に入れたツール設計を論じました。 不採録とする理由は人によりばらけていましたが、共通していたのは、論文中にエビデンス不足の部分があるという批判でした。また、面白いがこの学会向きではない、というコメントもありました。
最終的に、絵コンテの現在と未来の話だけでは説得力に欠けるのだろうと考えるに至り、過去まで調べてメディア研究として報告したのが今回の講演ということになります。正直なところ、それぞれの不採録理由には思うところがありますが、どちらかが半端なかたちで通ってしまっていたら今ほど掘り下げなかったかもしれません。この研究の本来の内容が、一本の論文として書くには大きすぎたのだと、今では思っています。
HCI の限界
専門である Human-Computer Interaction (HCI) について人に説明するとき、自分は「人とコンピュータのよりよい関係を考え、試作し、検証するプロセスの学問」というふうに言っています。比較的新しい学問分野なので定義は未だに揺らいでいますが、コンピュータが関与していることは最低条件の一つです。
また、コンピュータ科学の一分野なので工学的なアプローチが好まれる傾向にあり、論文全体が簡潔なロジックで書かれていて、読者が知りたいと思う内容が箇条書きでリストアップできるようなものが多数を占めています。稀にエッセイのような論文が通っていますが、業界の重鎮のような人でないとなかなか書けないでしょう。
今回の研究についていえば、もともと紙とペン(とストップウォッチと設定資料の束)で書かれていたアナログの絵コンテそのものは HCI 研究の対象になりません。そのデジタル化がどこまで進んでいるか調査したり、進んでいない場合、どうすれば進むか議論し提案したりする内容なら、 HCI 分野の研究といえます。
難しいのは、絵コンテのデジタル化の話をする前に、絵コンテという日本に固有のフォーマットについて説明しなければならない点です。国際学会に投稿する以上、読者の文化的な背景がまったく違うことも考慮し、グローバルな読者の興味を惹くようにしなければなりません。
商業アニメの作り方が英語の文献でまとまっていて、引用できれば、少なくとも絵コンテがその中で重要な位置を占めていることについては簡単に説明できるのですが、そういった文献はほとんど知りません。ここでいう文献は HCI に限らず、論文でなく書籍でも Web サイトでもよいのですが…もしご存じの方がいればぜひご教示ください。ちなみに、自分の知る数少ない英語リソースの一つが Jarrett Martin さんが運営している YouTube Channel Tonari Animation (旧: Striving for Animation) です。
このように、研究トピックがアナログ由来かつローカルなものの場合、HCI 分野の研究としてはきわめて大きなハンデを背負うことになります。
論文の限界
ここまで HCI 分野ならではの難しさを書いてきましたが、それが克服できたとしても、分野によらずなおも残る制約があります。それが、知を共有するための標準様式、論文が持つ限界です。
論文の書き方を解説した書籍はいろいろありますが、おそらくどれにでも書いてあるポイントとして「一論文一トピック」ということが挙げられると思います。論文の重要な構成要素にタイトルと要旨があり、本文まで読まなくても、論文でいったいどんなことが議論されているか(どんな問題が解決されているか)把握できるようになっているべきです。逆にいえば、一本の論文の中で話したいことの交通整理ができていないと、タイトルや要旨が分かりづらくなるか、本文との関係がちぐはぐになってしまいます。
つまり、論文で扱うべきトピックには適切な粒度があるということです。自分は学生の頃これを意識するのが苦手で、論文の本旨と関係ないことを語りがちでした。そこで以前 @drinami 先生に指摘されたのがこのツイートで、未だによく覚えています。
論文や登壇発表などは、他の研究者に面白さを伝えるためのコミュニケーションです。そうして面白さの観点を共有した人たち同士が集まるのが学会であり、定期的に最新の面白い知見を持ち寄るのが研究会だったり会議だったりします。研究が進展し、これまでの学会では収まらないくらい仲間が増えると、新しい研究分野ができます。
論文は読者がいてこそのメディアであり、研究を進めるためのツールであるということは、大事な観点だと思います。一本の論文にするとうまく伝わらないテーマは、交通整理を行い、トピックごとに切り分け、複数の論文にするべきなのです。それか、自分の手に余る場合、諦めて他のテーマを探すしかないこともあります。実際のところは、こちらが大多数でしょう。人類の知は未だ限られていて、面白い研究テーマはそこかしこに潜在しているのですから、心配することはありません…。
研究の知と論文
分野の限界と、知を伝えるフォーマットの限界。自分で書いていてなかなか耳が痛くなってきました。ただし、どちらもそこまで気にしなくていいのだ、というのがいちばん言いたくてこの記事を書いています。
なぜ気にしなくてよいかというと、分野に限界を感じたら違う分野を探せば(作れば)いいし、論文は途中経過報告にすぎないからです。
幸いなことに、人類の興味は留まるところを知らず、大変な数の学会が存在しており、話が合う人は世界で探せばどこかに一人くらいはいるはずです。特定のコミュニティに所属することで話の合う友人を作る機会が棄損されているとしたら、もったいないことです。過度に恐れず、いろいろな場に顔を出してみる好奇心が大事だと思います。
また、完璧な論文というものは存在しません。研究には複数の文脈があって当然ですが、イントロダクションは一本筋を通さないと読みづらくなります。関連研究は著者と査読者の視界に入らなければ抜け落ちます。メソッドは常に発展途上だし、評価実験には再現性問題が付きまといます。議論が尽きることはなく、 future work に約束された研究がそのままのかたちで進むことなどほとんどないのです。
研究という営み自体は、究極的には自分が面白ければ勝手に続けられます。人類には早すぎるということもあるでしょう。その孤独は身が切れるような痛みを伴うこともありますが、あとから振り返れば意外と愛おしくも思えるものです。戦略的な話をするならば、分野で文脈が共有されていない研究トピックというのは、逆にチャンスでもあるのです。なぜなら、研究の重要性がコミュニティ内で共有された瞬間に、それまでのハンデが、ブルーオーシャンのメリットに反転するためです。
なかなか高尚なことを言いづらい、考えづらいご時世であることは確かです。それでも研究が本来持っている自由と、そこで生み出される孤独な知が論文という特殊フォーマットに乗っかってコミュニティに浸透していくプロセスについて、大切なことを忘れないように書き留めてみました。
最後に、こうして息の長い研究をサポートしてくれているアーチと、そうした活動の社会的な意義を認め兼業として許可してくれている産総研、それぞれの上司の面々に感謝します。
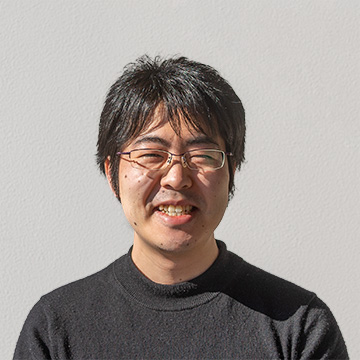 トップ
トップ